(アフィリエイト広告を利用しています。)
今回は、国民年金のお話です。
日本国民である以上、20歳になったら国民年金に入らなくてはいけません。幸か不幸か強制加入です。
20歳から60歳までの40年間収めることが義務となっています。
サラリーマンは、知らないうちに?意識しなくても?勝手に給料から引かれていますが、学生の場合そうはいきません。
国民年金には学生のための制度があるので、それらを利用する場合はきちんと手続きをしておく必要があります。
ブログのタイトルにもなっていますが、一番オトクに国民年金を納める方法は親が子供の年金を納めて、親の年末調整で取り戻す方法です。
私自身、サラリーマンを20年以上続けていますが、普通に働いているだけではなかなか知りえない情報でした。
40代になり、自己投資に目覚め、FP(ファイナンシャルプランナー)を取得しました。
FPの学習過程や取得してからもお金に関する情報が自然と入ってきた知識です。
こどもの国民年金を納めることもそうですが、自己投資にFPの学習はオススメです。
ぜひ、最後までお付き合いください。
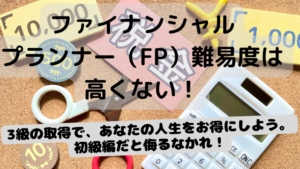
学生とは、大学生・大学院生・高等専門学校・特別支援学校・専修学校および各種学校などに在籍する学生のことを指しています。
被保険者の種類と保険料
被保険者とは国民年金に入っている人のことを言います。逆に保険者とはこの場合、”国”ということになります。
国民年金には第1号、第2号、第3号の3種類の被保険者があります。
種類と納付方法は次の通りです。
第1号被保険者
(対象者)自営業者、農業等に従事する人、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法) 自分で納めます。
第2号被保険者
(対象者)厚生年金保険の適用を受けている事業所で働く人。いわゆるサラリーマンなど
(保険料の納付方法)厚生年金に入っていると自動的に国民年金にも加入しているので給与からの天引きです。
第3号被保険者
(対象者)第2号被保険者の配偶者かつ扶養されている20歳以上60歳未満の人。ただし、年間収入が130万円以上の人は該当しません。
(保険料の納付方法)配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
上記の通り、20歳の学生の場合、第1号保険者になります。
何も手続きしない場合は強制的に毎月16,590円(令和4年度の保険料)の保険料を納めることが義務となります。
(令和3年度と比べると実は20円減額されています。)
納付方法はサラリーマンなら自動的に給与から引かれますが学生の場合、自営業者などと同様に自分で支払いの手続きをしなければなりません。
支払いを怠ると年金支給金額が減額されたり、将来おいてずっと納めないと“年金無支給”といった事態に陥ってしまいます。
この月額16,590円は学生にとってはかなりの負担になるのではないでしょうか。
![]()
学生納付特例制度
そこで、たくさんの収入がないと想定される学生には学生納付特例が利用できます。
学生本人の年収が128万円以下(扶養している家族がいない場合)の場合に適用されます。
ひと月の収入が10万円を超えてくるようならこの制度は利用できないかもしれないので注意が必要です。
学生の間は保険料を収めなくてもいい制度ですが、納付を免除されているだけで、収めなかった期間の年金は減ります。
でも将来受け取る年金を減らしたくない場合は、追納制度を利用できます。それが学生納付特例制度です。
追納は、学生生活が修了し、社会に出てお金を稼げるようになったあとから保険料を納める制度ですが、免除されてから10年以内に納めなくてはなりません。
追納が完納されている場合は、将来受け取る年金が減額されることはありません。
親が子供の年金が払ったら節税になる
もう一つは、学生の保険料を親が納めるという方法です。
大学や専門学校の学費は、家計を圧迫するお金ではありますが、将来のことや節税を考えれば、この方法は最良です。
年間の保険料は約20万円になりますが、親がこの保険料を支払い、自分の年末調整や確定申告の際に書類を書くことで社会保険料控除分として一定金額が戻ってきます。
1年間の国民年金の保険料(令和4年度)
月額16,590円 × 12ヶ月 =\199,080-
社会保険料控除の金額は親の課税所得によって変わってきます。
所得税率が10%の方は約4万円、所得税率が20%になる方は約6万も戻ってくることになります。
可能であるなら、これを利用することがベストな選択かと思います。
所得税は課税所得が多いほど税率が高くなる税金です。いわゆる累進課税制度です。
納める国民年金の金額は年間約20万円と決まっていますが、税率が高くなると戻ってくる金額が多くなります。
子供が後から追納しても、社会保険料控除の対象となりますが、通常、子供が親の収入を超えるのは、かなり年齢を重ねてからということになります。
なので親が変わりに払っておいた方が、家族全体としての節税効果が高くなることが見込まれます。
課税所得とは以下の計算式で計算されます。
課税所得 = 収入 - 所得控除 - 給与所得控除 - 社会保険料控除
所得控除は扶養の人数など、様々な条件で変わってきます。
節税額の概算です。(扶養人数や扶養者年齢によって変わります。)
- 年収400万円→ 課税所得315万円→ 税率10%→ 節税額約4万円
- 年収700万円→ 課税所得529万円→ 税率20%→ 節税額約6万円
自分の課税所得が気になる方は直近の「源泉徴収票」で確認してみてください。
そうすると今年の課税所得の予測がつくのではないでしょうか。
| 課税所得金額 | 税率 |
| 1,000円~194万9,000円 | 5% |
| 195万円~329万9,000円 | 10% |
| 330万円~694万9,000円 | 20% |
| 695万円~899万9,000円 | 23% |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% |
| 4,000万円 | 45% |
課税所得(収入)が多ければ、税率が高くなるので、税率に比例して戻ってくる金額は多くなります。
4000万円以上の課税所得がある親は納税額の45%も戻ってくることになります。
不公平感を感じますが、お金持ち優遇の政策とも読み取れます。
大学・専門学校の学費に加えて、更に親が年間20万円を負担することになりますが、この部分だけでも奨学金を借り払っておいた方がかなりお得になります。
税金を取り戻す方法は「年末調整」または「確定申告」で書類を書いて戻ります。
下の図は年末調整の申告書ですが、「社会保険料控除」の欄に必要事項を記載の上、会社の経理に提出しましょう。
ここで注意があります。必ず、親の名前で子供の保険料を納付してください。
そうしないと年末調整の際に返還されません。

まとめ
この記事では書きませんでしたが、国民年金には「老後の年金=老齢年金」のために納付するイメージが強いかもしれませんが、障害を負った際の障害年金、遺族を亡くした際に支給される遺族年金の保険料を同時に納めている年金とも言えます。
民間の医療保険や障害保険に入るなら、まずは国民年金を納めましょう。
そのほうが絶対にお得です。
年金の未払い問題が大きく取り上げられる時期もありましたが、国が国民を保証してくれる大切な保険制度の一つです。
民間の保険が魅力的にみえることがあるかもしれませんが、まずは国民年金に加入しておくことが大切ではないでしょうか。
日常生活ではなかなか得られない知識を紹介しました。
FPはお金の知識を高めるには最高で取り組みやすい資格です。
国民年金だけでなく「ライフプランニング」・「資産運用」・「年金・保険」など広く知識を得られます。
国民年金を収めた後は、FP取得に取り組んで人生をお得にしてみるのもオススメです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
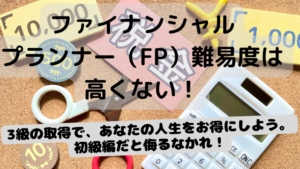
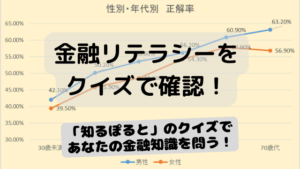
![]()




コメント